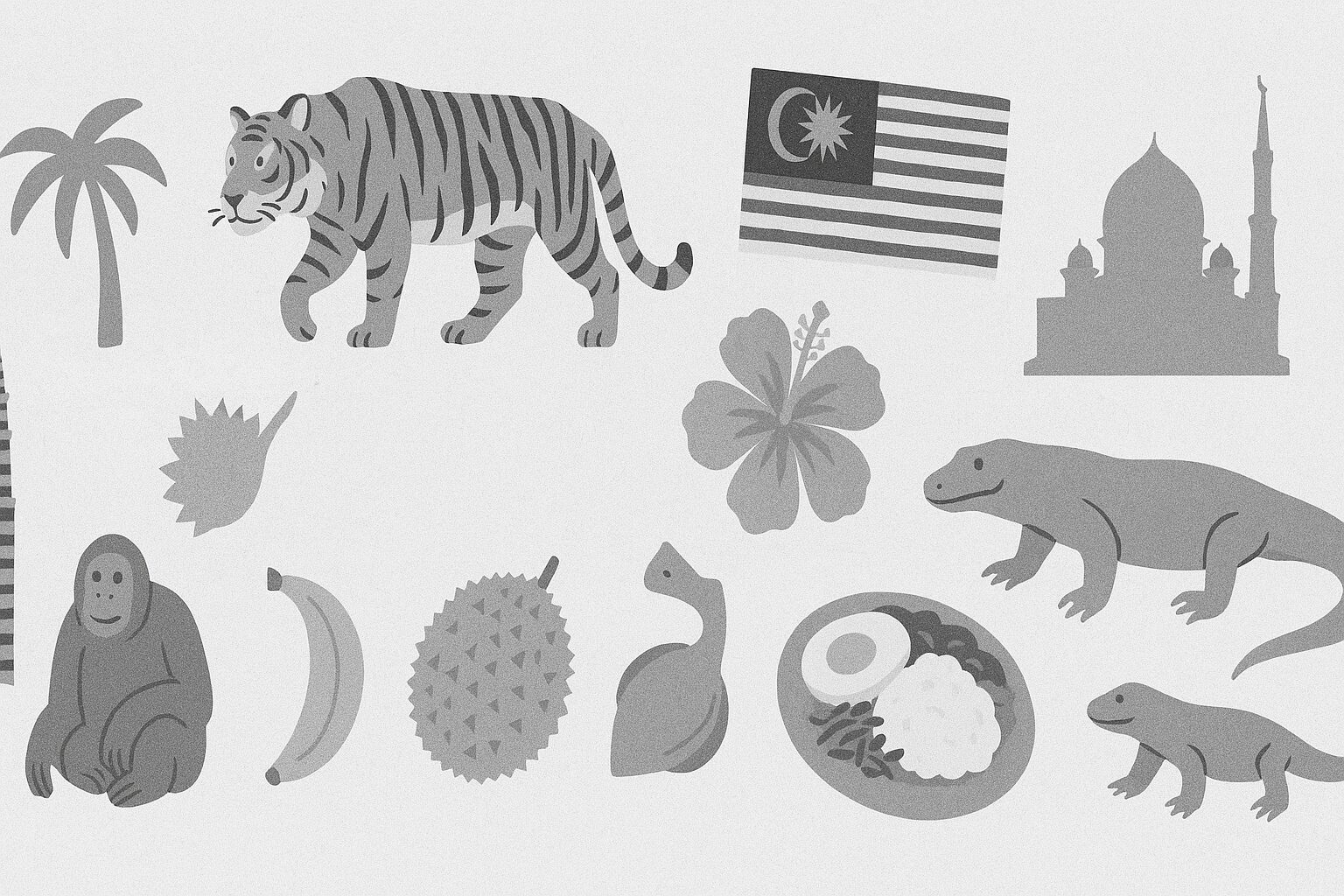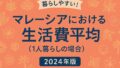考えていることを書き綴ります。
いつもとは少し違うスタイルのため、お見苦しい箇所もあるかと思いますがお許しください。
自己紹介
まる(@maru_Chuotto)です。
IT企業を退職して、駐在夫としてマレーシア移住中の一般男性です。
帯同生活で感じた“自分の居場所のゆらぎ”
マレーシアに来て早くも1年が経ちました。暑さにも、喧騒にも、さすがに慣れてきたような気がします。最近になって、漠然とした不安に突然襲われることがあります。実はこちらの記事に書いた神経痛を発症してしまったのもストレスが原因でした。
頼れる人も少なく、自分で自分を守るしかないという状況が続く中で、心と身体が無理をしていたようです。
2023年に妻の海外赴任が決まったとき、「家族はできる限り一緒に」と思い、迷いなく帯同することを決めました。結果的に、現地就職もできて、生活もある程度安定してきました。それは本当にありがたいことだし、自分なりに一歩一歩進んできたという実感もあります。
ただ最近、「この先どうなるんだろう?(特に自分)」という不安は頭から離れません。
今の仕事を選んだ理由は、キャリアを積み上げるためというよりも、「職歴のブランクを空けないこと」が目的でした。異国の地で、慣れない生活の中で、いちばん大切にしたかったのは「家族と過ごす時間」「安心できる日常」。これは自分で選んだことで、今でもその選択に後悔はありません。
ただ、キャリアを一時的に“横に置いた”ようなこの選択は、安らぎをくれる一方で、未来の自分を見失わせるような気もしてしまう。
妻は日本に戻れば職場が待っています。それに対して私は、帰国後の保障はありません。今の仕事が続く保証はないし、帰国後に何ができるかも分からない。比べても仕方ないと分かっていても、妻と比べてしまって、自分のことを責めたり、頼りなく思ってしまうことがあります。
そしてもうひとつ、最近気づいたことがあります。
「妻の海外駐在」という家族で掲げたミッション。これが、帯同前の数年間を支える心の軸になっていたように思います。それを達成してしまった今、心にぽっかりと穴が空いたような感覚があります。
「自分はどこに向かいたいんだろう?」「これから、何を叶えたいんだろう?」
自分自身の気持ちや願いに耳を傾けることを、少しだけ後回しにしていたのかもしれません。「家族ではなく、自分は何を実現したいのか」という問いへの向き合い方が今後のテーマになってきそうです。これは、働いているかどうかに関係なく、「駐在帯同」という立場にある人なら、きっと一度は感じるものなのかもしれません。
共働き世帯の割合は増加しており、夫婦がともにキャリアを継続することが一般的になってきています。その一方で、日本企業の海外赴任制度においては、いまだに「駐在員=働く本人」「帯同配偶者=支援役」という旧来的な家族モデルが暗黙の前提として残っており、現代の多様な夫婦のあり方とのギャップがあります。
駐在員家庭においては固定的な役割期待やジェンダー規範が残りやすい構図になっていること、そしてその“ズレ”が当事者に心理的な負担をもたらしている可能性が高いと思っています。
・駐在員本人と帯同配偶者は、海外赴任にあたってどのような役割を互いに期待しているのか?
・その期待がズレたとき、帯同配偶者はどのような心理的影響を受けているのか?
・帯同配偶者がどのように自己を再構築し、役割期待と向き合っているのか?
駐在帯同経験者の約80%がメンタル不調を実感したと回答しているデータもあります。
(※【駐妻キャリア総研・研究結果報告】駐妻・駐夫のアイデンティティクライシス、メンタルヘルスについて – 帯同中約80%が経験するメンタル不調の実態と対応策 )
ただ、こうした帯同者の語りは、まだまた社会的には少ないように感じます。
身をもって体感したメンタルヘルスの大切さ。どのように広めていくのか、サポートしていくことができるのかをじっくりと考えていきたいと思っています。